
諭し、救ってくれる物語
今回は、藤岡陽子さんの小説2作品をご紹介します。看護学校が舞台の「いつまでも白い羽根」と、シングルマザーの新聞記者と戦力外通告を受けたプロ野球選手が織りなす物語「トライアウト」(ともに光文社文庫)です。
藤岡さんについては、#18でご紹介した木村元彦さんの「13坪の本屋の奇跡」で知りました。同書には、隆祥館書店の「作家と読者の集い」のうち4人のライブが掲載されているのですが、そのうちの1人が藤岡さんでした。
そこでは、店主の二村知子さんは、藤岡さんの作品について次のように語っています。
「藤岡さんが書かれたものは、『いつまでも白い羽根』も、とてもメッセージ性があって、人の生きる姿勢を語っておられます。『トライアウト』も嫌なことがあっても、ぜったい逃げない姿勢を見せてくれる物語です。そしてそれは今を生きていく私たちを諭してくれるような、救ってくれるような作品だと思います」

本当の強さと優しさの形を描く
「いつまでも白い羽根」は藤岡さんのデビュー作で、文庫本カバーには次のようにあります。
「大学受験失敗と家庭の事情で不本意ながら看護学校へ進学した木崎瑠美。毎日を憂鬱に過ごす彼女だが、不器用だけど心優しい千夏との出会いや厳しい看護実習、そして医学生の拓海への淡い恋心など、積み重なっていく経験が頑なな心を少しずつ変えていく…。揺れ動く青春の機微を通して、人間にとっての本当の強さと優しの形を真っ向から描いた感動のデビュー作」
著者の藤岡さんは1971年京都市生まれ。大学卒業後、報知新聞社に入りますが3年半で退社、タンザニアの大学に留学しマラリアに感染するなど死を身近に体験したといいます。帰国後、30歳で慈恵看護専門学校に入学。卒業して看護師となり、同時に小説を書き始めたそうです。
そんな藤岡さんですから、看護学校の日々、特に授業での実習や看護実習などはとてもリアルに描かれています。以下に引用する個所なども、看護学校に学んだ経験があるからこそ書けるものでしょう。
「患者という他人と正面から向き合わなくてはならない実習で、学生たちはかけがえのないものを得るが、それと同時にたくさんの苦しみとも出合わなければならない。病床にある人と、学生という身分で関りあっていく難しさというのは、実習を経験した者にしかわからないと、瑠美は思う。
自分が資格を持った看護師であれば、患者の力になることもできるけれど、学生という身分では患者からもらうばかりで、自分は何ひとつ返すことができず、それがまた苦しいのだった」
この作品には、いろいろな登場人物がでてくるのですが、モデルとなる人がいるそうです。「13坪の本屋の奇跡」で紹介されているのですが、主人公の木崎さんは藤岡さんの親友だった人、その友人の千夏さんのモデルもいるそうです。クラスメイトには34歳の佐伯さんという人もいるのですが、藤岡さんは「一番その人に近いかな」ということです。
そのうえで藤岡さんは、こう話しています。
「懸命に勉強して看護師を目指す人がいっぱいいて、その感動を『いつまでも白い羽根』に書かせていただいたんです」
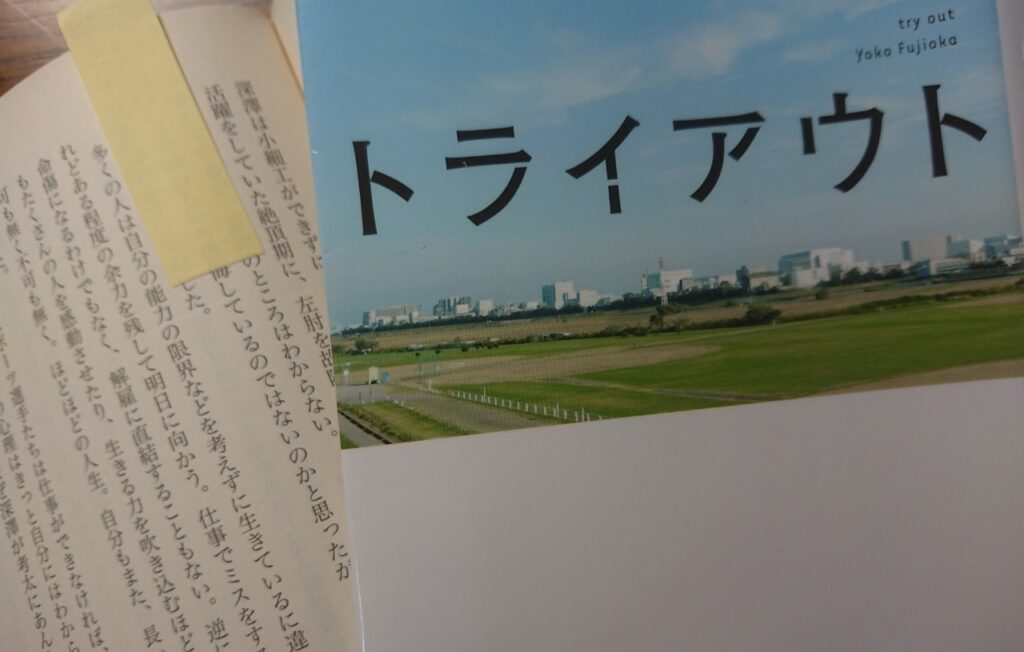
自分を励ますような気持に
一方の「トライアウト」は、「戦力外通告を受けながら、他の球団に入るためのテスト、トライアウトに挑む元プロ野球選手とそれを取材するシングルマザーの新聞記者との出会いを軸に、不器用ながらも前向きに人生を進んでいこうとする様が、切々と丁寧に綴られて」(「13坪の本屋の奇跡」)います。
藤岡さんは報知新聞を3年半で退社しましたが、ある取材をきっかけに、「光が当たる人もいて、そうじゃない人もいて、でも自分は光が当たらなくても頑張り続ける人、を書きたいんだと思ったんです。それならもうスポーツ新聞では書けないな」と会社を辞めたといいます。
二村さんは、藤岡さんについて「取材対象に対する目線がすごく柔らかいんですね」と語り、この本を読んだときに「すごくリアルやし、それでいて優しさがある。この本は、シングルマザーや、人生をやり直そうとしている人に絶対薦められる」と思ったそうです。
本書に、主人公の久平可南子が野球場を訪れ、「芝がきれい。球場ってどこも芝生が鮮やかですよね」と、「あまりに美しい芝の緑に」素直に感嘆の声を上げるシーンがあります。それに対して、戦力外通告を受けたプロ野球選手の深澤はこう答えます。
「職人たちが真剣に維持してるからな。グランドを整備する人たちも真剣。選手も真剣。球団を運営している人たちも真剣。野球記者も真剣。ファンもまずまず真剣。そういう場所なんだな、プロ野球ってのは。たかが野球、されど野球。スポーツなんて要は娯楽かもしれないけど、それを命がけでやっている人間たちで守られてる場所なんだ」
この目線の柔らかさ、温かさは、可南子や深澤を取り巻く人たちにも向けられています。解説で瀧井朝世さんは「本書は家族小説でもある」といい、「久平家の人々の、それぞれの可南子の見守り方が丁寧に描かれている」と書き、続けます。
「心配しているからこ辛い言動で娘にあたり、確執を生んでしまった父親の謙二。影が薄いようでいて、実はそっとみんなに寄り添っている母親の佳代。(以下略)」。魅力あふれる人々ばかりです。
なにより息子の考太です。「彼に関わるエピソードが、どれもこれもあまりにも素晴らしすぎて言葉を失うくらい胸に迫」ります。「彼の家族に対する愛、母親を守ろうとする姿、野球に対する夢と希望、母に似たのか弱音を吐かずに生きようとする健気さに心を打たれっぱなしだ」。私も同じでした。瀧井さんは、最後にこう書いています。
「大切なものを大切にする、その尊さや、人生のトライアウトがうまくいかない時は、依怙地になってその場に留まるのではなく自分が変わっていくことの必要性を教えくれるこの物語。
過去は変えられないけれども、大人だって人生を何度もリスタートできるし、そうやって自分で道を選んでいったなら、未来はきっと明るいと素直に信じさせてくれる。私は今、解説を書きながら、自分を励ますような気持になっている。それくらい、この小説は沁みた」
私も励まされました。沁みました。