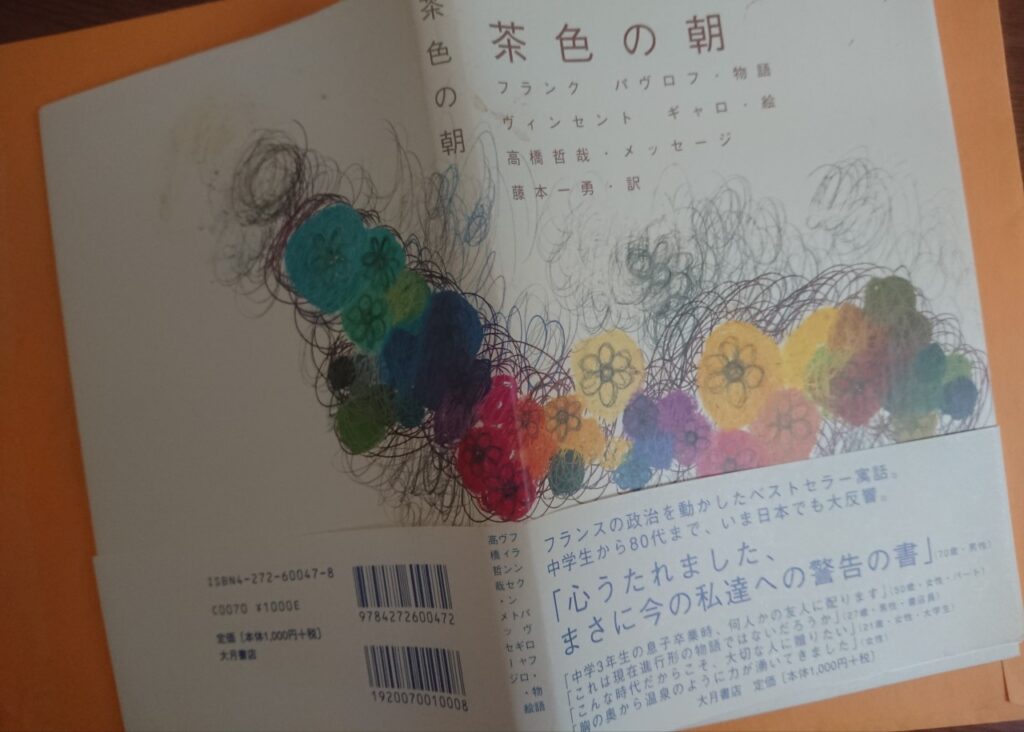
全てが茶色だけになってしまう。猫も犬も、服も歌も、そして新聞もラジオも「茶色」以外のものの存在は許されなくなってしまう…。「茶色の朝」は、そんな不気味で恐ろしい、ある国を描いた寓話です。
この本は、フランスのフランク・パヴロフ氏の原作に、ヴィンセント・ギャロ氏が日本語版のために描いた絵、さらには哲学者の高橋哲哉さんのメッセージを加え、2003年に大月書店から出版されました。
物語は、語り手である「俺」と、友人のシャルリーがビストロでコーヒーを味わいながら語らう風景から始まります👇

「俺」はシャルリーから愛犬を安楽死させたと告げられますが、「さすがに驚いたが、ただそれだけ」でした。「俺」も先月、自分の猫を始末していたからです。
茶色以外のペットをとりのぞく「ペット特別措置法」ができたためです。「お国の科学者たちの言葉によれば、『茶色』を守るほうがよい」からです。なぜなら「茶色がもっとも都市生活に適していて、子どもを産みすぎず、えささえもはるかに少なくてすむことが、あらゆる選別テストによって証明された」というのです。
それはペットでとどまりません。その法律を批判していた新聞が発禁になり、新聞は「茶色新報」だけになります。茶色党による茶色化はどんどん進み、過去においても茶色以外のペットを飼っていた人、その家族も「国家反逆罪」で逮捕されてしまいます。はたして「俺」はどうなるのでしょうか。
高橋哲也さんは、「やり過ごさないこと、考えつづけること」と題したメッセージの冒頭で、なぜ「茶色」なのかについて書いています👇
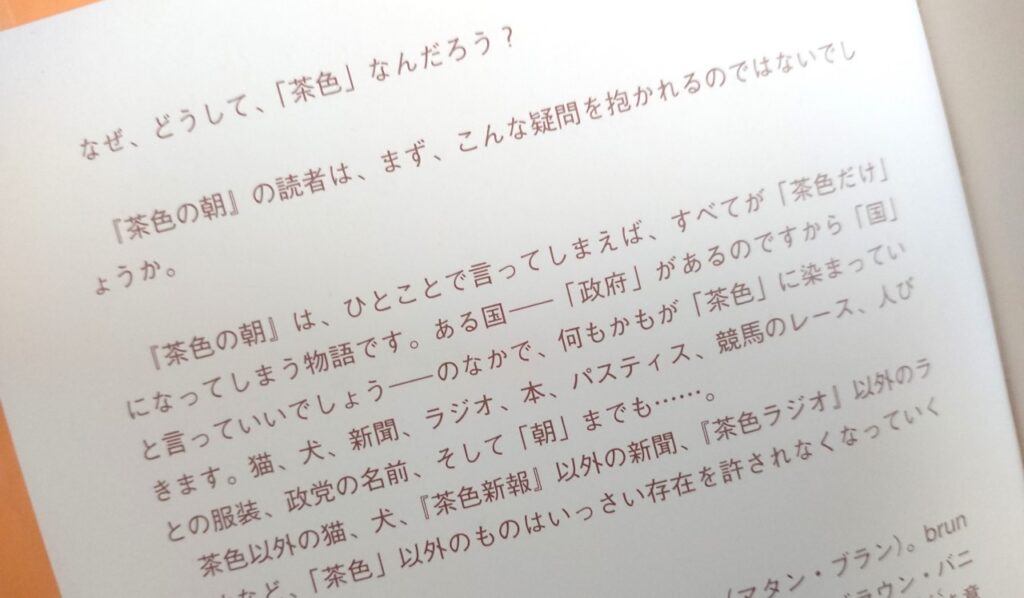
「フランスの読者にとって、茶色brunはナチスを連想させる色」です。「ヒトラーに率いられたナチス党(国民社会主義ドイツ労働党)は、初期に茶色(褐色)のシャツを制服として着用していた」からです。
さらには「そのイメージがもとになり、今日ではもっと広く、ナチズム、ファシズム、全体主義などとも親和性をもつ『極右』の人々を連想させる色になっています」といいます。
「俺」について高橋さんはこう書きます。「出来事のひとつひとつにとまどったり、不安を感じたりしながらも、そのつどなにかの理由を見つけて、出来事をやり過ごしていきます」。
さらには「『俺』とシャルリーがそうであるように、人びとは、自分自身が直接深刻な被害にあわないかぎり、『茶色』の広がりをやり過ごしていきます。『茶色に守られた安心、それも悪くない』と」とも書きます。
「『流れ』に逆らわなければ」、安心で安全だし、「流れに『抵抗』して『ごたごた』に巻き込まれる」より、おとなしくしている方が得策だからです。
「茶色の朝」を迎えたくなければそうすればいいのか?高橋さんは以下の通りに書いています。
「自分自身の驚きや疑問や違和感を大事にし、なぜそのように思うのか、その思いにはどんな根拠があるのか、等々を考える必要があるのです」。そして、「勇気をもって発言し、行動することは、考えつづけることのうえにたってのみ可能なのです」と、この「メッセージ」を締めくくっています。
「国」に限らず、会社などどんな組織についてもいえるのではないでしょうか。全部で50ページもない本です。ぜひお手に取り、考えてみていただければと思います。